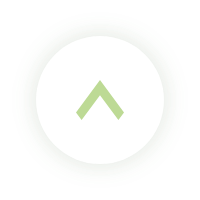理念と行動基準
理念と行動基準
理 念
愛を原理とし、
秩序を基礎とし、
進歩を目的とする
方 針
質の高い全人的な
医療・介護・予防を
シームレスに展開し、
皆様に愛され信頼される
存在となります
行動規範
- 私たちは感性を磨き、自らを高めていきます
- 私たちは一人一人の人格を尊重し幸せな暮らしを支えます
- 私たちは明るい健全な運営を行い社会へ貢献します
行動指針
自己研鑽
~ Self Improvement ~
常に自己を振り返り、自己研鑽に努めます
顧客志向
~ Customer Engagement ~
あらゆる顧客と愛着ある深い絆を築きます
プロ意識
~ Pride of a Professional ~
自分たちの仕事に責任と誇りを
もって取り組みます
共働・協調
~ Teamwork ~
チームの一員であることを意識した
行動の実践に努めます
意識改革
~ Motivation & Challenge ~
変わることを恐れず、新しいことへの
挑戦を行います
2023年4月1日
社会医療法人 きつこう会 多根総合病院
病院長 小川 稔
患者さまの権利や医療安全管理について
病院概要
病院概要